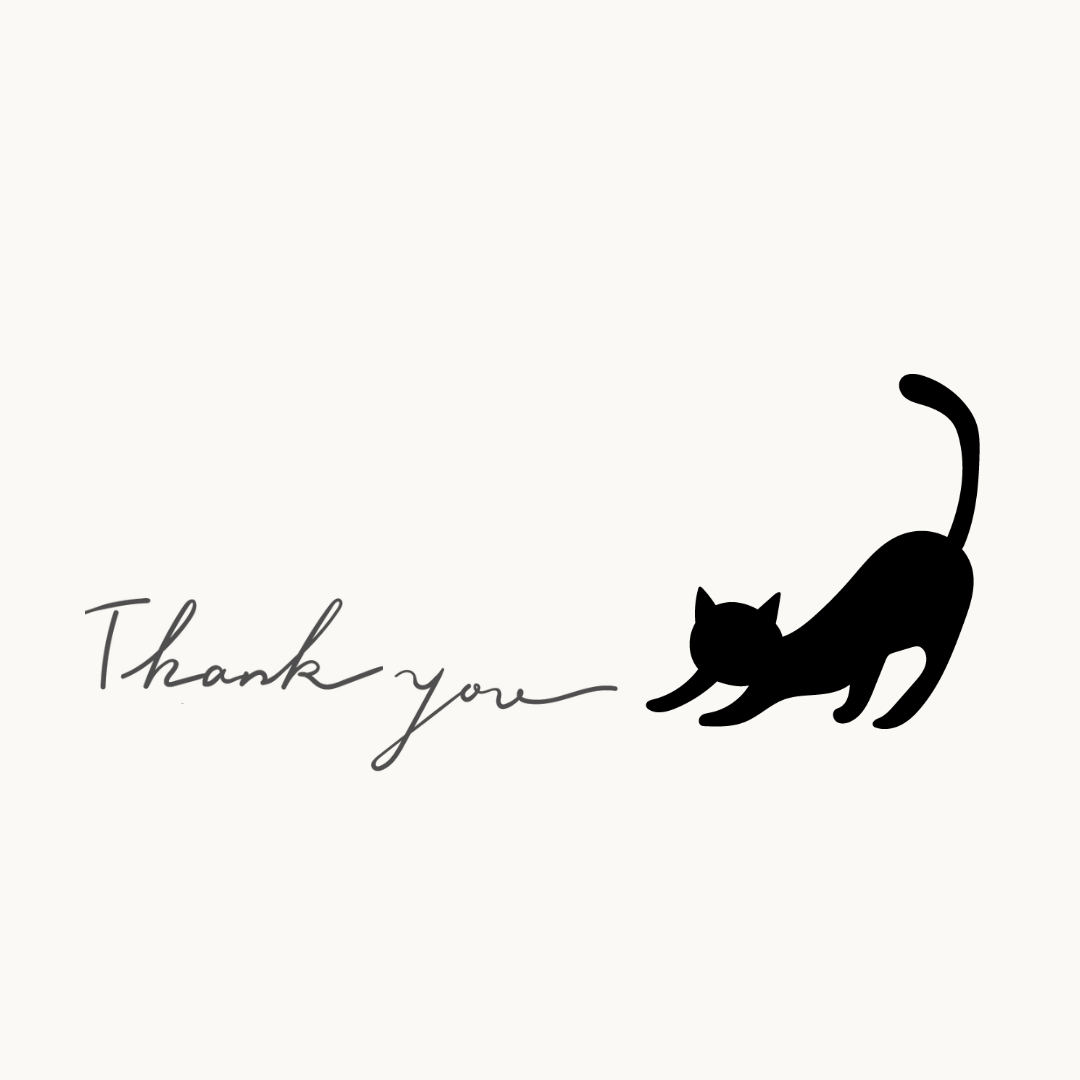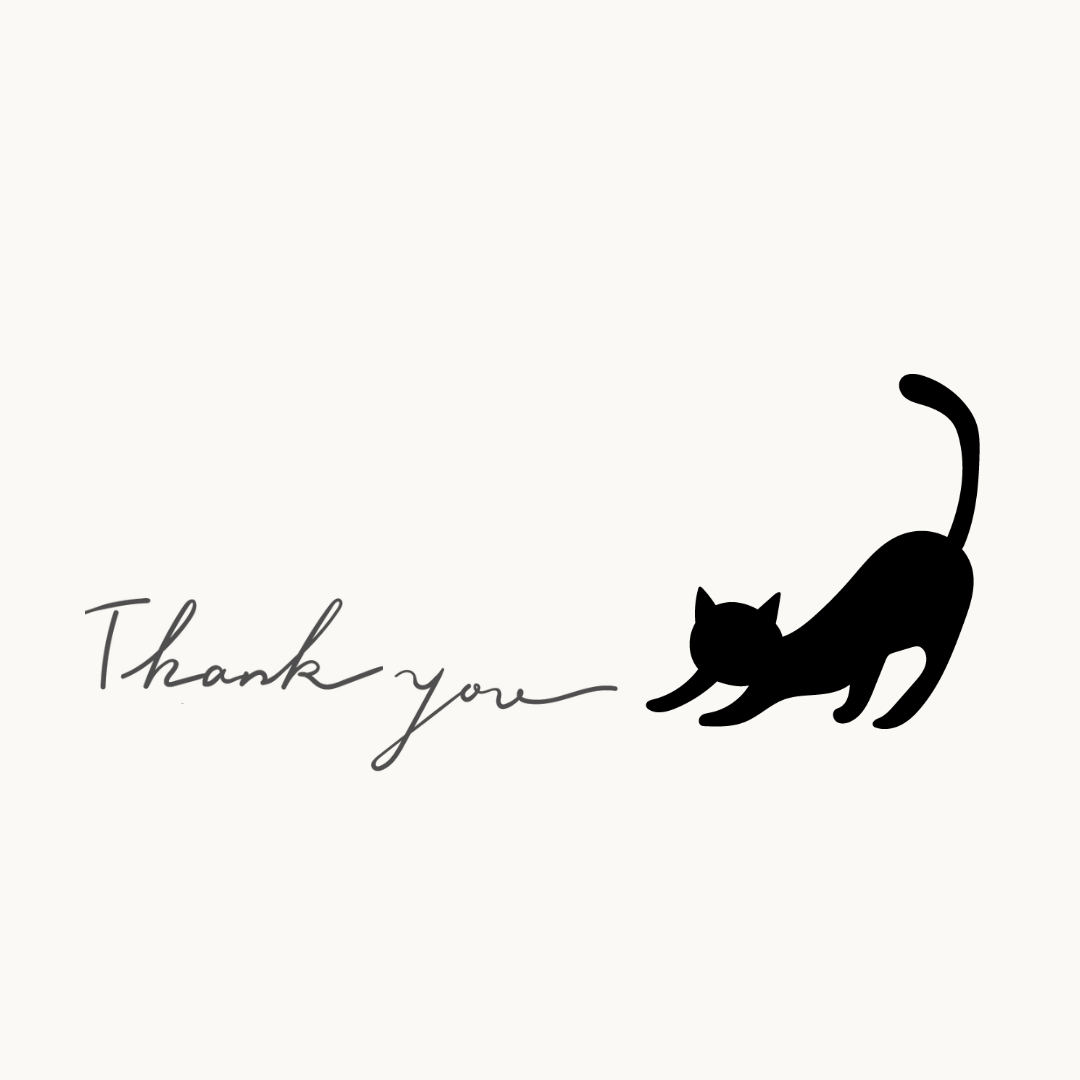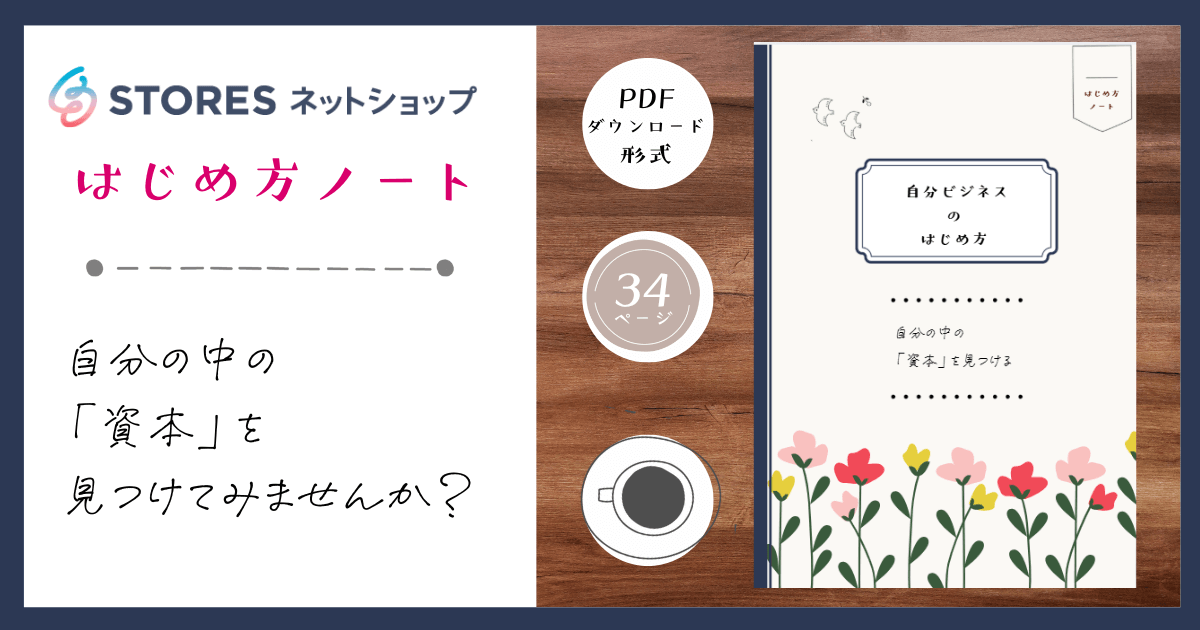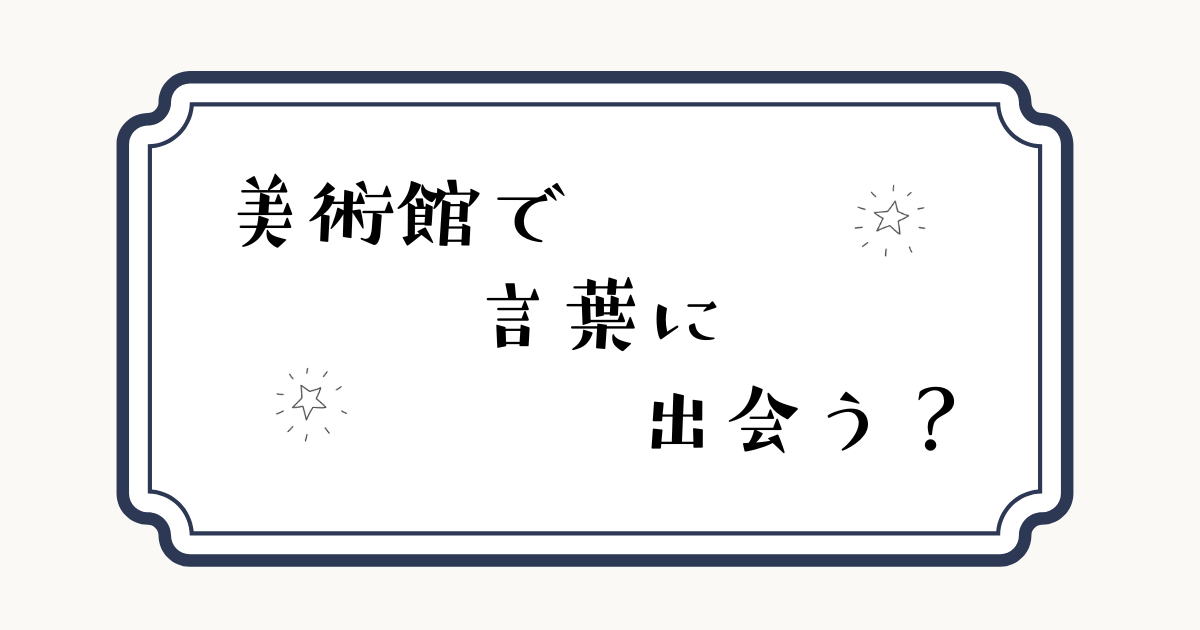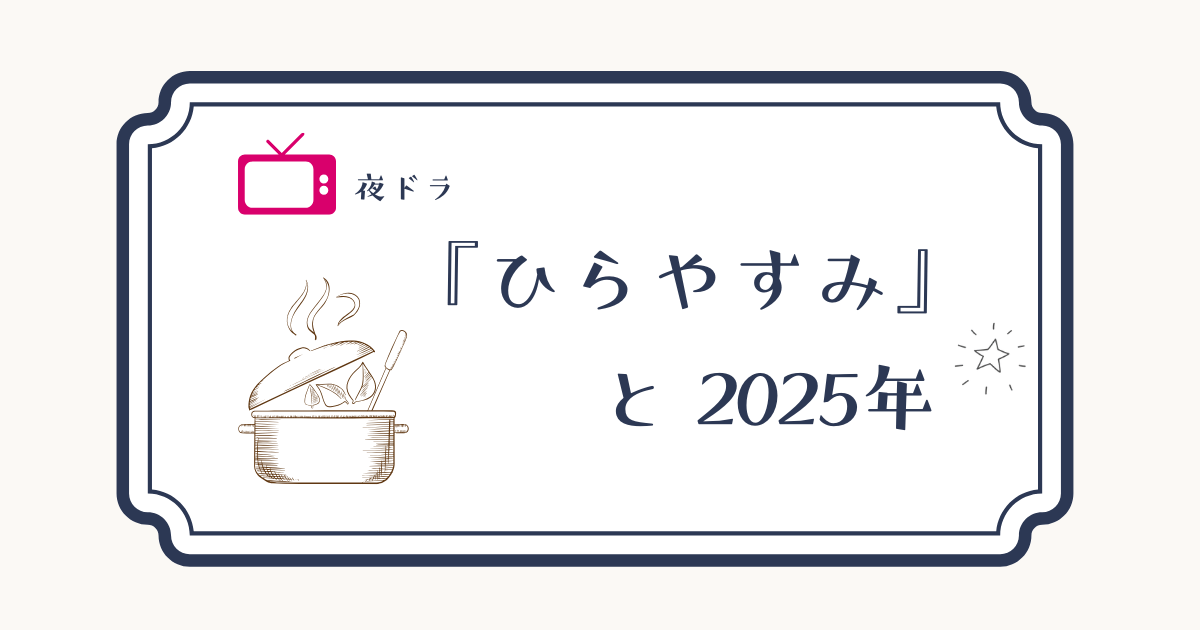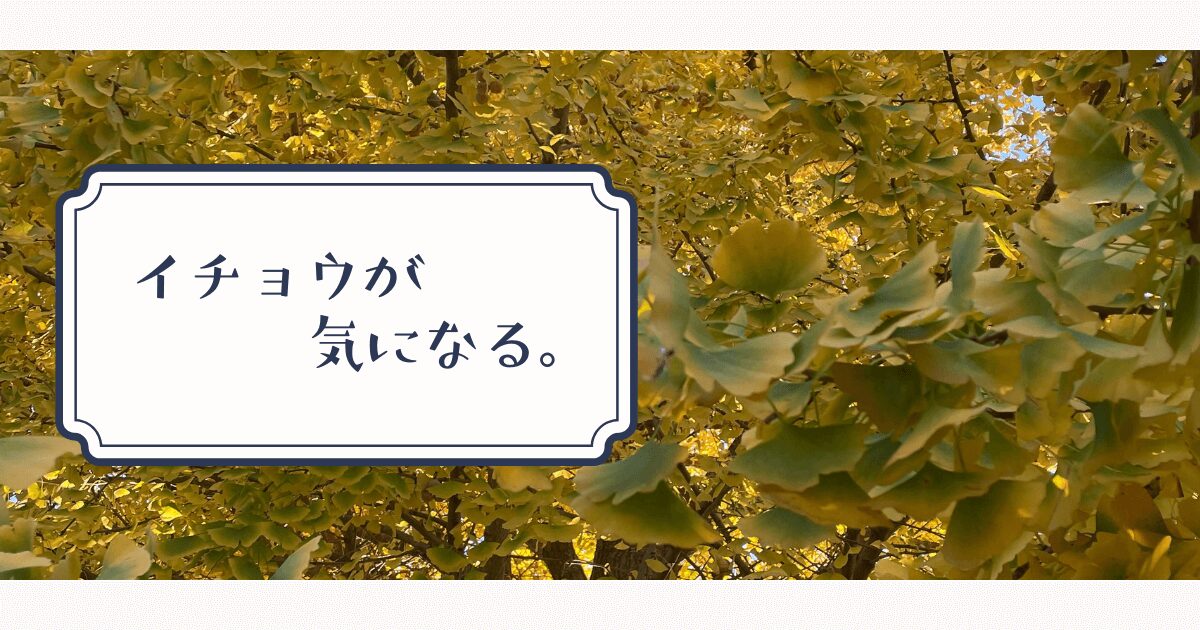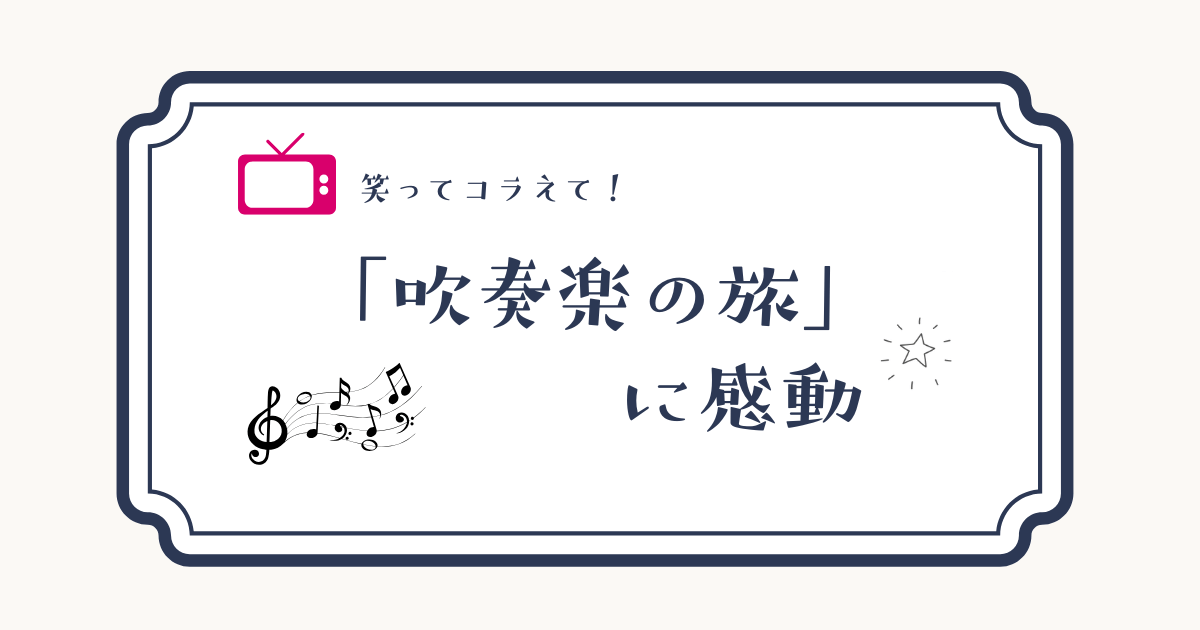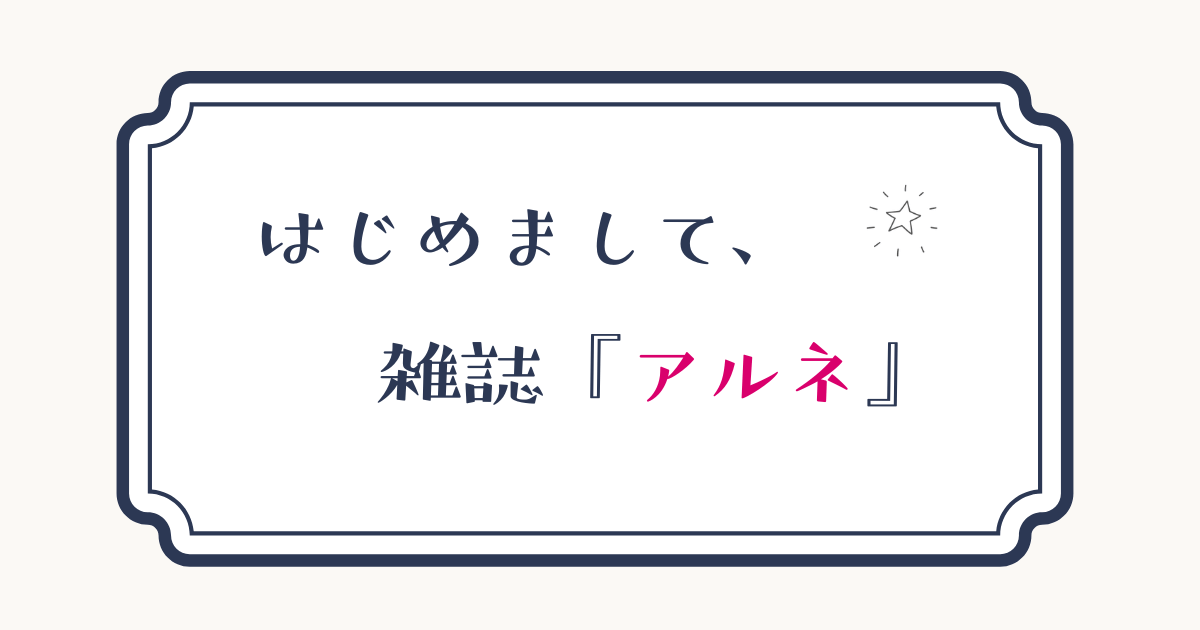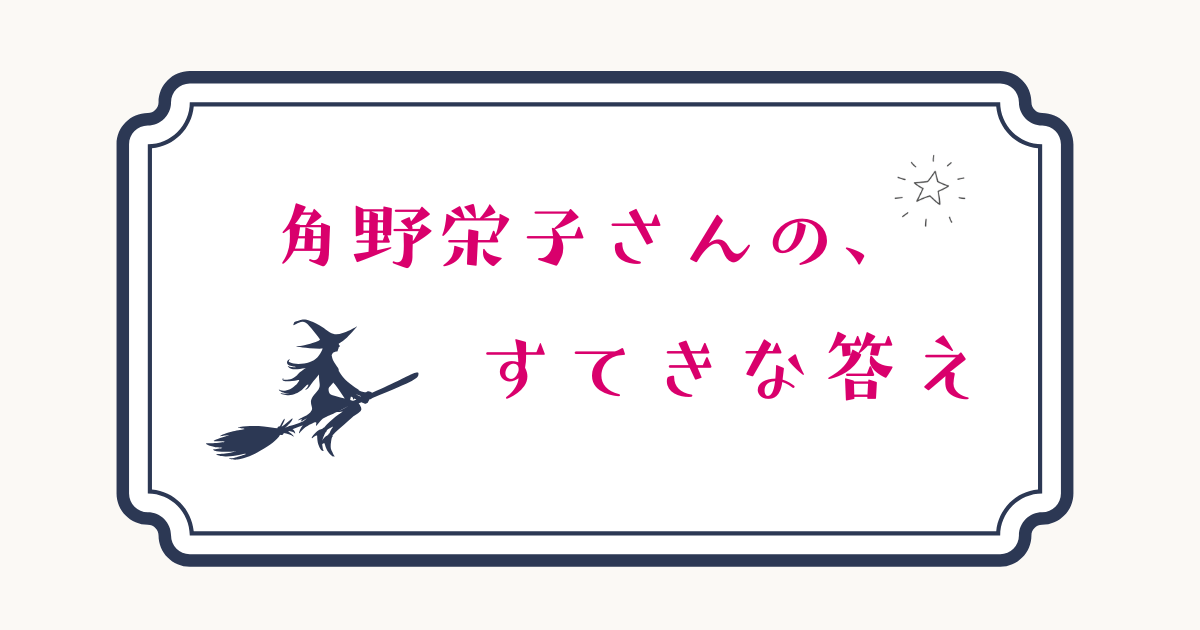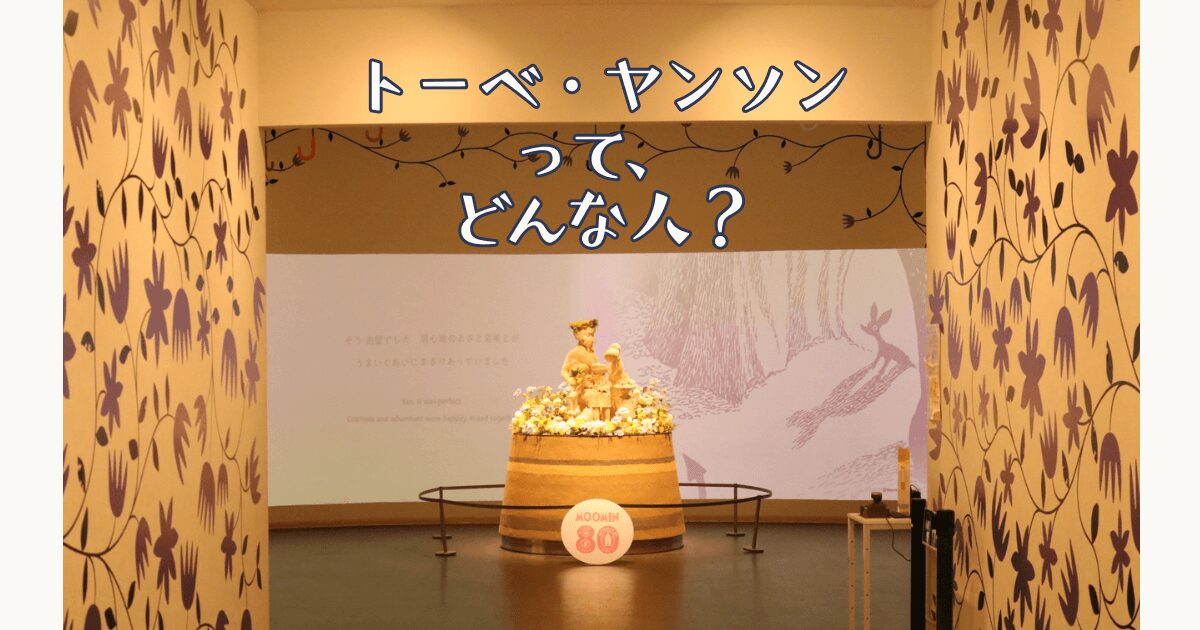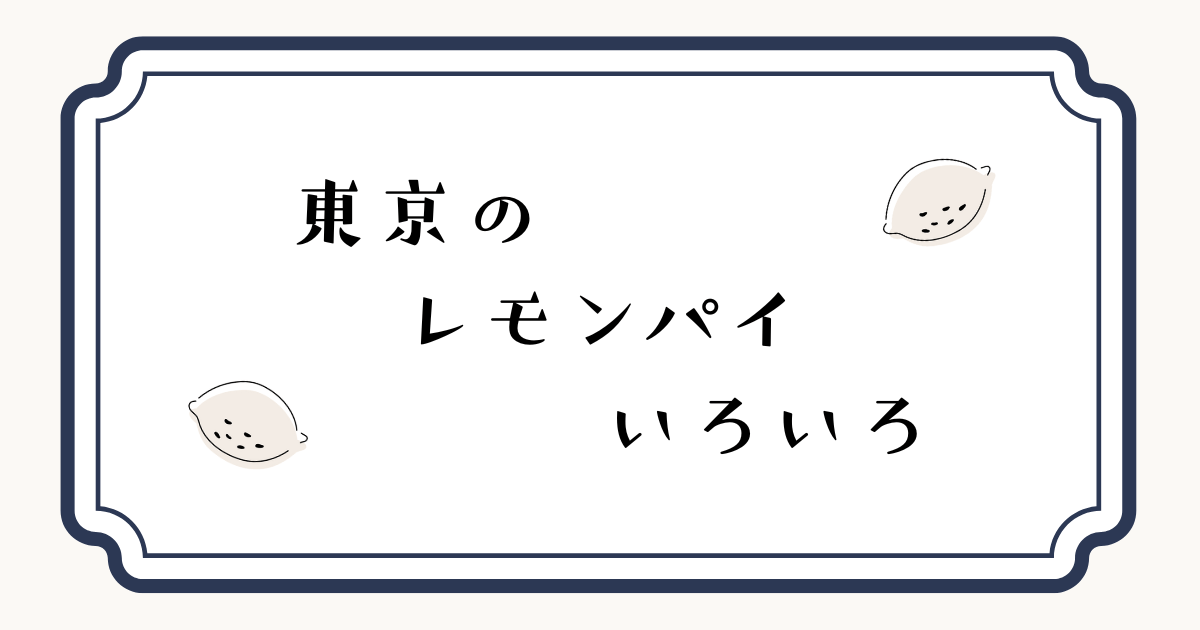ミロの大回顧展が見たくて東京都美術館へ行ったときのことです。
ミロを浴びまくって、ふと、展覧会を出ると、入場無料のコーナーが。
なんとな~く足を踏み入れたそのコーナーは実験的な展示がされていて、文化祭のような雰囲気でした。
その中で、「パブリック・ファミリー実行委員会」というチームの展示に興味を惹かれました。


『わたしの・いる・ところ』 工藤春香
工藤春香さんという方の展示は、「日本の家族に関する政策の年表」が印刷された布が張り巡らされていました。
それは「壁」の役割をしていて、3つの部屋が作られていて、各部屋にはちゃぶ台やテーブルが置かれた生活空間になっているのです。
この年表は1870年~2025年までの「日本の家族に関する政策」なのですが、すっごく重いというかなんというか。
朝ドラ『虎に翼』を思い出し、ひとつひとつに「はて?」と言いたくなるような。
なんとも言えない政策のオンパレードでした。
昭和14年(1939年)には、今の『あんぱん』にも出てきた「結婚十訓」も出てきました。
国が個人の生き方に口を出すという恐ろしいことがまかり通っていたことに戦慄しますが、年表を追っていくと、今も大して変わらないような気もしてくるのがまた怖い。
例えば、「こども家庭庁」なんて未だに国家が個人の生き方に口を出す気満々ですよね。
「家庭」を入れることに固執し、絶対に選択的夫婦別姓を導入したくない、議論もしたくない!という与党が勝ち続ける国…。
年表の最後では、2024年の出生数が70万人を切るのですが、当然の帰結のように思えました。(というか、オチになっている)?
この展示の意図について、パンフレットにはこのように記されていました。
この作品では、国の家族政策の変遷を表すとともに、どこにも可視化されない、複雑で矛盾した生を持つ個人の「家族の物語」を通して、自分にとっての「家族」とは何かを問いかける試みである。
『わたしの・いる・ところ』 工藤春香
自分にとっての「家族」とは何か?たしかに、めちゃくちゃ問いかけられました。
歴史上、国家は家族制度、道徳教育、メディアなどを使ってそれぞれの時代に適した「家族のあるべき姿」を提示し、私的領域である家族の内面に干渉してきた。
人間は家族という集団の中の「役割」をもつ以前に「個人」である、という考え方は、極めて近年のものである。
本当に!人間は「個人」であるという考え方は、未だに進歩的過ぎて世界中でハレーションが起きている気がします。。


衝撃の一言
そのパンフレットには、工藤さんの個人的な体験も書かれていました。
それは、自宅のキッチンの高さの話。
工藤さんの自宅のキッチンの高さは85cm。
ワークトップ(作業台)の高さは、日本工業規格(JIS)により、80cm、85cm、90cm、95cmに定められていて、日本のシステムキッチンでは85cmを選ぶ人がほとんどだそうです。
そして、85cmがちょうど良いのは身長160cmの人。
日本の成人女性の平均身長は158cm。
つまり、家庭用建売住宅のキッチンの作業台は、この家族の中にいる成人女性がキッチンに頻繁に立つということが想定されていることになります。
社会は、自分が決めるよりも先に、あらゆることが「すでに決まっている」
私は、この家庭用住宅によってこのキッチンを使って家族の中で一番頻繁に料理をする、ということは「すでに決められて」いた。
実際はどうなっているかに関係なく。
我が家(築30年の賃貸マンション)の作業台も測ってみたら、85cmでした。
169cmの私は、腰をかがめて生きるしかない!
国産ベビーカーの持ち手の高さも、台所の高さも合わない!!
と、常々思っていましたが、それ以前に、ベビーカーも台所も、「母」である私が使うことが「すでに決まって」いたんだ…。
家にいる母親の行動は、既に住居の空間の中で「決められている」
しかしこの違和感も、生活していく中でいつの間にか消えていく。
私は料理を作りながら、リビングでゲームをしている子どもに宿題はやったのかと声をかける。
この「決められている」行動を私は求められているのだ。おそらく。
というか、自分の意志で選んで決めてきたと思っていることの大半は、「すでに決まっている」ことであり、「選ばされている」だけなのかもしれません。
そのことに私は、あまりに無自覚だったと思い知らされました。



がーーーん!
これがアートなのだ
私がモヤモヤと、
「男子厨房に入らず」で育てられて、勉強と仕事だけしてきたオッサンの思い込みせいで私たちは要らぬ苦労を強いられているのではないだろうか。
などと思っていたことが、アーティストはこのように表現するのかと、自分の気持ちが立体となって目の前に表れ、多くの人と共有できた気がしました。
これがアートなのか。
ミロの“ついで“に入った、この入場無料の展示から、こんな気づきを得られました。
美術館って、アートって、面白いですね。